
糖尿病

糖尿病
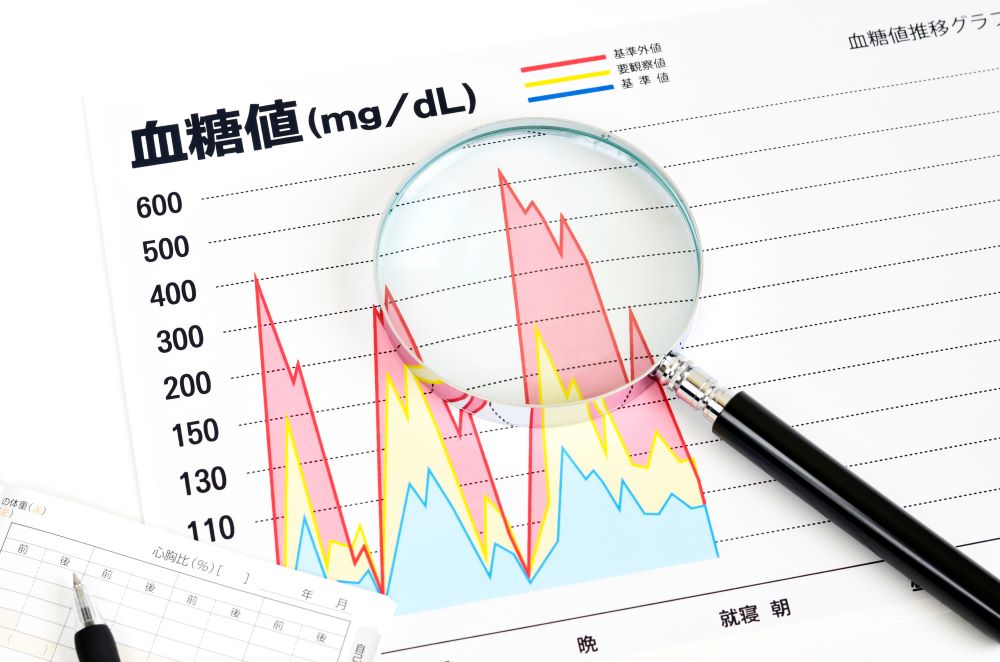
当院は、地域のかかりつけ医として「初めて糖尿病の可能性を指摘された」患者様にも多くお越しいただいています。糖尿病の治療と聞くと「不摂生な生活を怒られるだけでは?」と心配される方もいらっしゃるかもしれません。しかし、糖尿病は早期から適切な治療を行うことにより、合併症の発症リスクを抑え、健康寿命(自立して活動し、健康に過ごせる期間)を延ばすことができます。
少しでも不安のある方は、当院へお気軽にお越しください。

糖尿病とは、日常生活のエネルギー源であるブドウ糖が、何らかの原因により、細胞にうまく運ばれないためブドウ糖が血液中に過剰に残ってしまう状態(高血糖)となる慢性疾患です。血糖は生きていく上で非常に大事なものですが、あればあるほどいいというわけではありません。血糖値が高いまま放置されると、身体全体の血管が傷つき、合併症が引き起こされ、健康に様々な悪影響を及ぼします。血糖値を管理し、このような合併症を防ぐことが、糖尿病治療の主な目的になります。
しかし、糖尿病には大きな問題点があります。それは「症状が全くでない」ということです。そのため、自身が糖尿病であることに気付かない人が多いのです。また、すでに糖尿病と診断されていても、症状に気付かないために治療が遅れるケースも多く見受けられます。糖尿病は「サイレントキラー」とも呼ばれ、知らぬ間に身体をむしばんでいく恐ろしい病気なのです。結果的に、脳梗塞や心筋梗塞などの糖尿病合併症を若年で引き起こす恐れがあります。
糖尿病合併症は非常に怖いものですし、ある程度のところまで進行してしまうと、残念ながら元の健康な状態に戻すことが非常に難しくなってしまいます。しかし、糖尿病を早期に発見し、治療を始めることで、その後の健康状態の改善が期待できます。症状がないからこそ、定期的な診療と検査を受けることが重要となります。
糖尿病には大きく4つの種類があり、それぞれ発症の原因が異なります。
以下に、それぞれの原因と症状を紹介します。
2型糖尿病は最も一般的な糖尿病で、日本では10人中9人はこのタイプに当てはまります。
2型糖尿病は、以下のような人に起こりやすいことが分かっています。
2型糖尿病は、初期段階においては自覚症状が無いことが多く、「糖尿病合併症」が進行することにより、以下のような症状が少しずつらわれます
1型糖尿病は、自己免疫によっておこる病気で膵臓のインスリンを出す細胞(β細胞)が、壊されてしまう病気です。その結果、インスリンの量が足りなくなり、血糖値が上がります。
妊娠中はホルモンバランスの変化によって、インスリンの作用が低下し、通常時に比べると血糖値が上がりやすくなります。さらに、胎盤からはインスリンを壊す働きを持つ酵素が分泌されます。この酵素が必要以上に発生し、インスリンがうまく機能しなくなることにより、妊娠糖尿病を発症します。
妊娠糖尿病は通常の糖尿病と同様に自覚症状がほとんどありません。しかし、自覚症状がなくとも妊婦や赤ちゃんにとって重篤な病気を誘発する可能性があります。
その他の糖尿病には以下の2種類の原因が考えられます。
その他の糖尿病も通常の糖尿病と同様に自覚症状がない場合が多いです。
糖尿病は血糖値が高くなる病気です。しかし、高血糖だからと言って特別な自覚症状があらわれることはあまりありません。ではなぜ治療が必要なのでしょうか?
それは、糖尿病の治療が十分でないと、気付かぬうちに、様々な病気(糖尿病合併症)を引き起こし、健康に悪影響を及ぼす恐れがあるからです。
以下に、糖尿病の患者さんに特有な病気「三大合併症」と代表的な合併症を紹介します。
糖尿病は太い血管の障害「動脈硬化」の危険因子であり、狭心症や心筋梗塞など の心臓病、脳出血や脳梗塞などの脳卒中が起こりやすくなります。動脈硬化の進行を防ぐためには、食事後の血糖値の急上昇、高血圧、脂質異常 症、肥満を適切に管理することが大切です。中でも、食事後の血糖値の急上昇は 特に動脈硬化のリスクを高めるため、注意が必要です。
糖尿病網膜症は成人後の主要な失明原因の一つです。
「糖尿病で失明なんてありえるの…?」と、思われた方も少なくないことでしょう。しかし、糖尿病網膜症により、失明してしまう人は毎年3,000人以上と多く、成人後の失明原因のトップなのです。このような事態を防ぐためにも、少なくとも年に1回の眼底検査を行いましょう。
糖尿病性神経障害は高血糖によって神経が障害されることによって引き起こされます。多くの場合、手足のしびれが生じ、痛みのために睡眠不足やストレスに悩まされる方も少なくありません。しかし、しっかりと治療することにより、このような症状はいずれ軽快します。自覚症状がある場合は、早めに当院へご相談ください。
糖尿病性腎症は透析が必要になる原因の第一位です。高血糖で糸球体内の細い血管が障害され糖尿病性腎症が起こると、血液中に不純物が溜まり命の危険が生じます。そうなった場合、透析治療を始める必要に迫られます。
糖尿病の治療には、①食事療法、②運動療法、③薬物治療(経口薬、注射薬)があります。
糖尿病治療において大切なことは「適切な治療」を「継続」することです。糖尿病は「完治する」病気ではありません。
長期的な目標は、病気をコントロールし、合併症を防ぎ、健康な人と同じように生活することです。「適切な治療法」は私たち医療専門家が提供し、「継続」するのは患者さん自身です。どんなに良い治療法であっても、継続できなければ意味がありません。だからこそ、「無理のない治療」を行いつつ、「定期的に通院する」ことが重要です。
糖尿病にとって、食事療法は治療の基本であり、薬物治療やインスリン治療と並んで重要な要素となります。適切な食事療法を行うことで、血糖値のコントロールが可能となり、病状の悪化を防ぐことができます。糖尿病の食事療法において、特に注意すべきポイントを以下にご紹介します。
糖尿病の食事療法では80kcalを1単位として計算する食品交換表を活用したカロリーの計算をおこないます。食べる量をはかる「ものさし」です。 食品のカロリー計算は、栄養管理や健康維持に役立つ重要な情報です。それでは、カロリー計算の方法を見ていきましょう。
食品交換表は、糖尿病患者が食事療法において、血糖コントロールや栄養バランスを適切に管理するためのツールです。食品交換表は、主食・肉・魚・卵・大豆・乳製品・野菜・果物・海藻・炭水化物などの主要な食品群に分類され、それぞれの食品に対応する交換単位が設定されています。
食品交換表の利用方法は、まず自分の必要なエネルギーや栄養素の摂取量を計算し、それに応じて各食品群から適切な交換単位を選びます。次に、食品交換表を参考に、各食品の交換単位に応じた量を摂取することで、適切なカロリー摂取や血糖コントロールが可能となります。
1日あたりの適正なエネルギー量の計算には、下記の式が用いられます。
1日のエネルギー量の目安
エネルギー摂取量(kcal)= 身体活動量 ×標準体重
※1 身体活動量(kcal)
※2 標準体重(kg) = 身長(m)× 身長(m) × 2 2
|
軽い労作 |
25~30 (kcal/kg目標体重) |
|---|---|
|
普通の労作 |
30~35 (kcal/kg目標体重) |
|
重い労作 |
35~ (kcal/kg目標体重) |
日本人の摂取塩分量は高く、高血圧や腎臓病の原因となることから、厚生労働省は1日当たりの摂取目標量を食塩相当量として18 歳以上の成人男性で7.5g 未満、女性で6.5g未満と設定しています。しかし、外食や加工食品の利用が増える中、塩分摂取を減らすことが難しくなっています。ここで役立つのが、日常の食生活での工夫です。
具体的には:
食事のバランスや栄養の意識も大切です。ナトリウムだけでなく、カリウムや水分の摂取にも注意しましょう。また、定期的に血圧を測るなど健康管理も欠かさないようにしてください。自分に適切な塩分摂取量を知り、健康的な食生活を送りましょう。
糖尿病の食事療法は、患者の年齢や体重、運動量などによっても異なります。個々の状況に合わせて、医師や栄養士・看護師と相談しながら食事療法を進めることが望ましいです。継続的に適切な食事療法を行うことで、糖尿病の予防・改善に大きく寄与します。
運動療法は、食事療法と並んで糖尿病治療の基本といえます。
食後に運動をすることにより、筋肉でブドウ糖や脂肪の利用が増加するため、食後の血糖値上昇が改善されます。また、運動を続けることによってインスリンの効きがよくなり血糖値がよくなります。さらに、中性脂肪は低下し、HDL(善玉)コレステロールは増加し、さらに血圧が下がるなどの効果もあります。
散歩・ジョギング・自転車・水泳などの有酸素運動を、1回に30分、週3回程度実施するとよいとされております。無理をしてしまうと、やる気を失ってしまったり、ケガをしてしまう恐れもあります。当院では患者さんの状態や生活スタイル、スポーツ歴の有無、持病の有無などを考慮して、運動メニューを提案していきますので、お気軽にご相談ください。
運動療法を行う上で注意すべきことは、低血糖です。その他の注意として、最初は散歩など軽い運動を短時間おこなうことから始め、次第に時間を長くして、強度もやや強くします。さらに運動中のけがや事故を防ぐため、運動前後にはストレッチング、ラジオ体操などの準備運動をおこないましょう。
以下の状態に当てはまる方は、運動がかえって身体によくない場合があります。運動を始める前に当院へご相談ください。
食事療法と運動療法を2-3か月継続しているにもかかわらず、良好な血糖コントロールが得られない場合、薬物療法を行う必要があります。薬物療法には経口薬と、大きく注射薬があります。
現在、日本では多くの経口薬を使用することができます。1種類だけではなく、複数の経口薬を組み合わせることで、良好な血糖コントロールが期待できます。
1型糖尿病の患者さんでは、インスリン注射による治療が一般的です。2型糖尿病の患者さんの場合、食事療法・運動療法・経口薬で治療しても効果が見込めないときにインスリン注射を開始する場合が多いです。